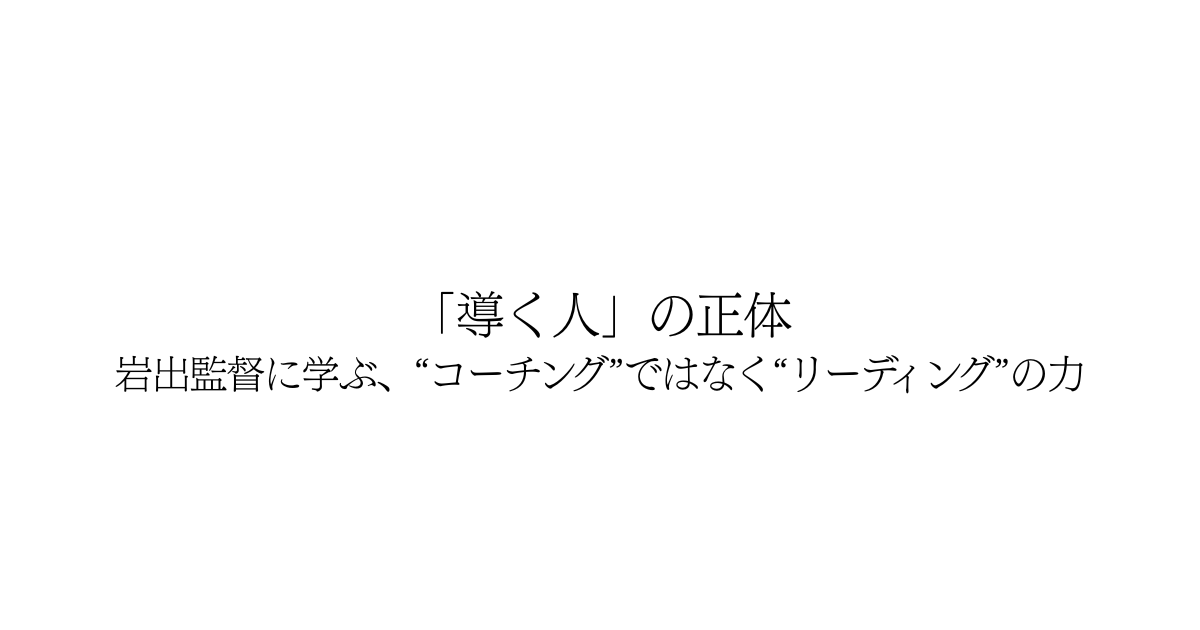
「導く人」の正体──岩出監督に学ぶ、“コーチング”ではなく“リーディング”の力
とある起業家の方とお話して気づかせて頂いたこと・・・
はじめに
今、求められているのは「コーチング」よりも「リーディング」かもしれません。
問いかけによって答えを引き出すのではなく、自らが一歩踏み出して“場を変える”行為。
その象徴とも言える人物が、帝京大学ラグビー部の岩出雅之監督です。
岩出監督は、かつて強豪とは言えなかった帝京大学ラグビー部を、大学選手権9連覇という歴史的快挙に導いた名将。
彼が行ったのは、厳しいトレーニングでも単なる勝利至上主義でもなく、「人間性を育てる場づくり」でした。
その哲学から、今の時代に必要な「リーディング(導く力)」の本質を考え直してみたいと思います。
【1】リーディング(牽引)という在り方に、岩出監督はどう向き合ったか?
「いい人間が、いいチームをつくる。いいチームが、強いチームになる」
――岩出雅之
岩出監督が行ったのは、戦術的な指導ではなく、“人づくり”による場づくりでした。
選手一人ひとりの価値観に寄り添いながらも、指導者自らが“背中を見せる”ことで、チームに空気と文化をつくったのです。
これはまさに、「場を照らすリーダー」=リーディングの実践者と言えるでしょう。
問い:あなたにとっての“リーディング”とは?
「“コーチング”ではなく“リーディング”が必要だと感じる場面は、私の身近にどんな場面だろうか?」
「私は“導くこと”を、どんなスタイルで実践しているか?」
「私は今、誰のために、どんな空気を照らせているだろうか?」
【2】組織=家族という最小単位でも、リーディングは生きる
岩出監督の言葉の中には、「家族的なつながりをチームの中にどう育てるか」という視点も見られます。
「誰かのために動けること」
「チームのために自分を律すること」
それはまさに、家族にも通ずる“組織の土壌づくり”です。
問い:あなたの“家族という場”はどう機能しているか?
「“家族”という組織の場の質が高いとは、どんな状態を指すのか?」
「“安心・安全の場”があると、人はどれほど自発的になれるのか?逆にそれがないとどうなるか?」
「私の家庭やチームで、“場の空気”が良かった時、どんな変化があったか?」
【3】意識的に動ける人を育てる“場”をどうつくるか?
岩出監督が育てた選手たちは、監督の指示がなくても自ら判断し、自ら動ける存在でした。
それは、単に厳しく鍛えたからではなく、
「その人がその人らしくいられる場」を整えたから。
リーダーの在り方が、無数の“自発性”を生み出していったのです。
問い:自ら動く人は、どう生まれるのか?
「“意識的に動けている人”と“なんとなく流されている人”の違いは、どこに現れるか?」
「私は今、どの領域で“無意識”から“意識的”に変化しようとしているか?」
「もし、世の中の10人に1人が“場を変える人”だとしたら、私の周りには何人いるか?」
おわりに
岩出雅之監督が証明したのは、
「人は場によって変わる」ということ。
そして、「場は人によってつくられる」ということ。
あなた自身が照らす側に立つとき、家族も組織も、チームも変わっていきます。
コーチングでは届かない深さに、リーディングの光が届く。
そんな時代に、私たちは生きているのかもしれません。

