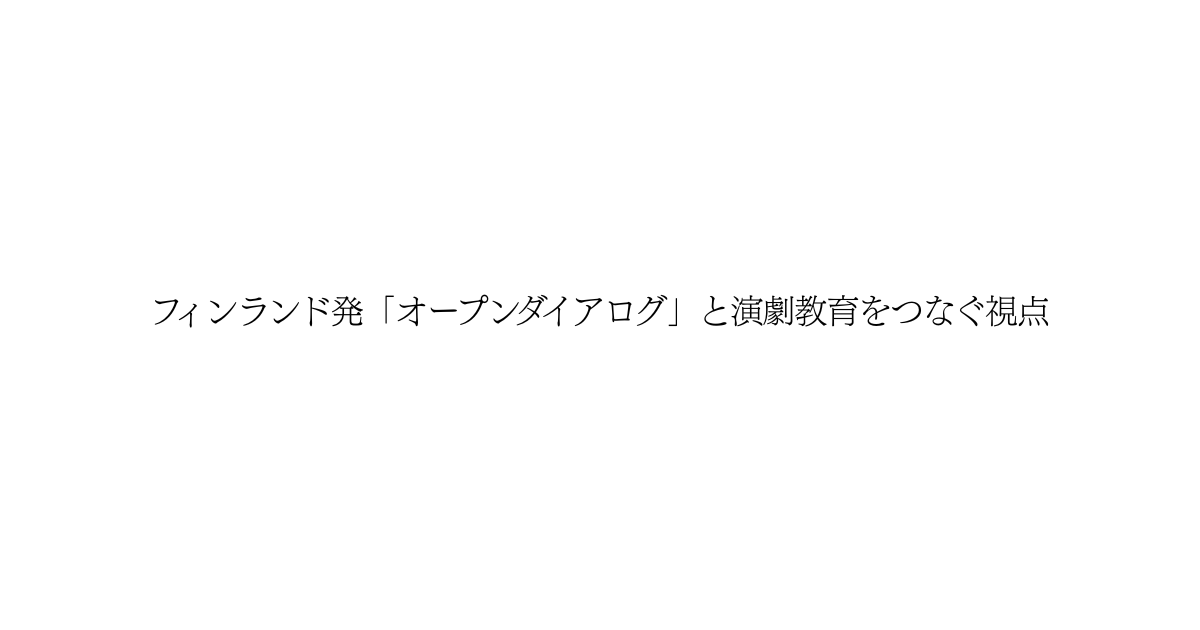
フィンランド発「オープンダイアログ」と演劇教育をつなぐ視点
はじめに
近年、日本でも「対話の質」を高める教育やコミュニティづくりが注目されています。
そのヒントとして、北欧フィンランドから生まれた二つの実践――
- 精神医療の現場で発展した オープンダイアログ(Open Dialogue)
- 学校教育に根づく 演劇教育(ドラマ教育)
があります。
一見すると無関係に思える両者ですが、共通しているのは
**「関係性を重視し、語りを共に創る」**という姿勢です。
オープンダイアログとは
オープンダイアログは1980年代、フィンランド西ラップランドで生まれました(Seikkula & Alakare, 2006)。
特徴は、当事者だけでなく家族や支援者を同席させ、治療方針や意味づけを「その場の対話」で決めていくこと。
専門家が結論を持ち込むのではなく、全員の声を等しく扱う点にあります。
7つの原則
- 即時対応
- 社会ネットワークを重視
- 柔軟性と訪問性
- 責任の一元化
- 心理的連続性
- 不確かさへの耐性
- 対話主義
特に「不確かさを急いで解決せずに共に語る」という態度は、日本文化における「すぐに答えを出す」傾向と対照的です。
成果
- 西ラップランドでの調査では、統合失調症初発患者の 80%以上が社会的に回復。
- 抗精神病薬の長期使用率も低下(Seikkula et al., 2006)。
- ただし自然主義研究が中心で、現在は英国でRCT(ODDESSIプロジェクト)が進行中(Pilling et al., 2022)。
フィンランドの演劇教育
フィンランド教育の柱は「対話と体験」。
2014年の基礎教育カリキュラム改訂では、
- 相互作用と自己表現
- 文化的コンピテンス
- マルチリテラシー
といった汎用的能力が明示され(FNBE, 2016)、演劇はそれを育む手法として活用されています。
実践の特徴
- 授業では即興劇やロールプレイを通じ、他者の立場を体験。
- 子どもたちは「安心して自己表現できる力」を育む。
- 自治体は「文化教育プラン」を整備し、劇場や博物館と連携して芸術体験を保障(Kangas, 2014)。
つまり演劇教育は「芸術」だけでなく、「民主主義を支える市民教育」として機能しているのです。
二つの実践に共通するもの
オープンダイアログと演劇教育の共通点は多くあります。
- 安全な場の保障
- OD:心理的安全性を確保
- 演劇:失敗を恐れず表現できる環境
- 多声性(polyphony)
- OD:当事者・家族・専門家の声を等しく扱う
- 演劇:役割を通じて多様な視点を体験
- 意味の共同創造
- OD:「症状の物語」を共に編集
- 演劇:即興の物語を協働で立ち上げる
この共通基盤があるからこそ、両者を結びつけると 教育・医療・地域づくりに横断的な応用が可能になります。
日本での応用可能性
日本社会は「空気を読む」文化が強く、本音を語る場が限られています。
ここにこそ ODと演劇教育のアプローチが役立ちます。
- 学校教育
→ いじめ・不登校への対応。ロールプレイ+対話で多様な視点を学ぶ。 - 地域福祉
→ 高齢者・若者・移民などが混ざる場で「共に生きる物語」を紡ぐ。 - 企業研修
→ ハラスメント防止や1on1面談で、ODの原則×演劇的シミュレーション。
おわりに
オープンダイアログと演劇教育は、
**「人と人が安全に出会い、共に意味をつくる」**実践です。
医療、教育、地域、ビジネス――すべての現場で応用できる可能性を持ちます。
日本でこれらを導入することは、
「すぐに答えを出す」文化から一歩引き、
「わからなさを共に語る」文化へ移行する挑戦でもあります。
対話と演劇の交差点にこそ、これからの社会を変える力が潜んでいるのではないでしょうか。

XANY.GEEKのナビゲーター / 俳優 / 建設業の社長
キョータ
学生時代はサッカー、就職せずに俳優の道へ(まだやってます)。家業でもあった仕事で起業して5期目を迎えて無事「建築業」取得して、人との繋がりとビジネスの歯車が嚙み合ってきました。大阪府高槻市で母親が美容師で自社の美容室運営をしてもらってます!https://beauty.hotpepper.jp/slnH000540300/ 口コミ満点は実は一度も口コミをお願いしたことがなくてリアルにご満足いただけてます。(母親の自慢)

